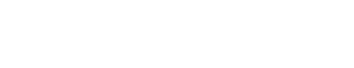収入合算
一般的なローンでは、借入れを希望する本人の収入を基準として借入可能額が決定されるため、希望額に満たないことも多々あるでしょう。このようなときに収入合算制度を利用すると、申込者本人の収入に合算者(配偶者や直系親族など)の収入を加えた金額が評価基準となります。
例えば、夫婦で収入合算をする場合、夫の年収が1,000万円、妻の年収が400万円であれば、合計1,400万円がローンの評価基準となります。ただし、これは両者が正社員のように安定した収入を得ている場合であり、妻が派遣社員やパートの場合は加算される割合が減ることもありますので注意してください。それでも、夫が単独で審査を受けるより評価額が上がる場合がほとんどですので、投資する物件の選択肢を広げることができます。
収益合算で税制上のメリットは得られるが、返済リスクは高まる
合算収入を選択した場合、税制上のメリットを受けられることもあります。合算者は、金融機関によって「連帯債務人」もしくは「連帯保証人」になるのですが、連帯債務人としてローンを一部負担したときは、合算者にも住宅ローン控除が適用されます。ただし、連帯保証人は契約者に返済能力がなくなったときにのみ返済義務が生じる性質のものですので控除は受けられません。
合算収入を利用する注意点として、「返済リスクが高まる」ことが挙げられます。例えば、夫婦で収入を合算した場合、夫が病気で退職を余儀なくされたときや、妻が妊娠をきっかけとして退職したときなど、どちらか一方が働けなくなると、返済負担が大きくなってしまいます。元々一人では負担できない金額を借りているわけですから、ローンを組んだ時点より収入が増えていないと、月々の返済はかなり難しくなるでしょう。
合算収入は、一人の収入では審査が通らなかったローンを、合算者の収入を加えることで融資が受けられる便利な制度です。しかし、利用する際は契約者本人とその合算者が「長期にわたって安定した収入を得られる」ことを確認し、慎重に検討する必要があります。
収入合算と関係の深い「総返済負担率」が融資の決め手
住宅金融支援機構などによる、一般的な住宅新築に関する融資、あるいは災害復興住宅融資、高齢者向け返済特例制度(部分的バリアフリー工事・耐震改修工事)の申込み条件は、「総返済負担率」で決まります。総返済負担率とは、自動車ローンや教育ローン、カードローンなども含む、その人のあらゆる借入れ返済額が、年収に占める割合を指しています。
負担率(%)=あらゆる借入れの年間返済額÷年収×100
<融資の申込み条件>
年収400万円未満の場合:総返済負担率30%以下
年収400万円以上の場合:総返済負担率35%以下
仮に、総返済負担率が融資申込み条件をクリアできなくても、まだチャンスはあります。住宅金融支援機構の許可を得て、同居する親族、あるいは同居しない直系親族(親や祖父など)の収入を足して、改めて計算できる場合があるからです。この収入合算で、総返済負担率の分母にあたる年収を増やすことによって、総返済負担率を減らし、申込み条件をクリアすることができる可能性があります。
例えば、年収300万円で、すでに契約している借入れの年間返済額が100万円の場合、総返済負担率は約33.3%となるため申込み条件をクリアできません。しかし、年収350万円の配偶者がいれば、合算で「年収650万円」となり、総返済負担率約15.4%で条件をクリアできるのです。
なお、収入合算は基本的に住宅ローンの申込みに使用するものですが、投資目的のアパートローンでも、条件によっては求められる場合があります。
親子で収入合算や夫婦で連帯債務を負う形のローンも存在
定年を直前に控えている人の場合、将来的な安定収入が見込めません。そのため、仮に融資が下りても返済期間を短く設定されてしまい、毎月の返済額が引き上がる可能性があります。そこで、20代、30代の働き盛りの子供(後継者)の収入を合算することで、通常のローンと変わらない返済期間を設定するという方法があります。同じ物件を引き継ぐことを前提にすることで、後継者の返済能力を基準に審査が可能となるのです。
また、金融機関の中には、収入合算した家族とのあいだで「連帯債務」を負わせる融資形式もあります。つまり、収入合算によって融資条件を引き下げる代わりに、収入合算の対象とした家族にも返済義務を負わせることによって、金融機関ができるだけ確実に回収できるようにしているのです。
ひとつの建物に複数の住宅ローンを組むペアローンとは異なりますが、それに近いメリットを享受し、リスクを各人が負担する結果になります。
この形態を採ると、返済負担を負う人数(家族や親族)が増える代わりに、融資額の条件が引き上がることが多くなります。また、複数の親族がお互いに債務を負う連帯債務関係にあるため、関わる全員が確定申告時に住宅ローン控除を利用できる節税メリットもあります。ただし、何らかの事情で返済ができなくなった場合のリスクを引き受ける必要はあるでしょう。