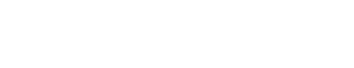使用貸借
「使用貸借」とは、物を貸し借りする契約のひとつで、民法第五百九十三条では「当事者の一方が無償で使用及び収益をしたあとに返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる」と記されています。
「無償」であって金銭のやり取りが発生しない点や、貸主が物を引き渡して初めて効力が発生する「要物契約」であることが最大の特徴です(口頭での約束のみで使用貸借契約を結んでも、物が手渡されるまえなら撤回できると考えられています)。そこは、契約当事者の意思表示の合致だけで成立する「諾成契約」である賃貸借などとの大きな違いでもあります。
また、使用貸借では物の借主が対価を支払っていないため、貸主に比べて「立場が弱くなりやすい傾向」があります。不動産の賃貸借では借地借家法で借主が特別に保護されますが、不動産の使用貸借で借地借家法は適用されません。ほとんどは家族や友人などといった、信用があり親しい関係において結ばれる契約となります。
使用貸借での貸主と借主の義務
使用貸借における借主は、他人の所有物を借りていることを自覚して注意しながら使用し、定められた時期に目的物を貸主に返す義務を負っています。返還時期が定められていない場合は、使用貸借の目的に従った物の使用や収益を終えた時点で、目的物を返さなければなりません。また、返還時期と目的、どちらも定められていない場合は、貸主から要求された時点で目的物を返さなければなりません。
貸主は、使用貸借の期間中に、自分の所有物を他人に使われることを受け入れる義務を負います。ただし、貸主は目的物に不具合が生じた場合に修繕する義務はありませんし、使用する上で最低限必要となる維持費などは、借主に負担させることができます。また、貸主は目的物に何らかの欠陥(瑕疵)があったとしても、借主に対する責任を負わないのが原則です。ただし、貸主がその欠陥を知りながら借主に告げなかったときに限り、責任を負います。よって、借主と貸主ともに、有償契約である賃貸借ほどは、法的にきびしい義務が課されているわけではありません。
なお、借主や貸主の立場が相続の対象となりうる賃貸借契約とは異なり、使用貸借契約では、借主が死亡した場合に契約が終了します(貸主の死亡の場合は終了しません)。使用貸借契約は、より個人的に密接な信頼関係が基礎になっているといえます。
使用貸借の借主にも独自の財産的価値がある
個人的な信頼関係に基づいているため、賃貸借に比べると厳格な契約ではなく、義務としても権利としても緩やかな使用貸借ですが、第三者からの権利侵害があった場合は、借主としての地位が財産的価値を帯び、損害賠償の対象となります。
最高裁判所の判例では、地上にある建物がなくなるまで(朽廃・滅失など)という期限で土地の使用貸借が契約され、建物を賃借していた人が失火で建物を全焼させたという事例で、土地の使用貸借人は建物賃借人に対して損害賠償を請求できると判断しました。二審の高等裁判所は、土地の使用貸借人に独自の財産的価値は認められないとし、損害賠償請求権も否定していましたので、最高裁判所はその判決を破棄したことになります(最高裁判例:事件番号/平成3(オ)825より)。
このケースから、使用貸借の期間が早めに来たことによって、使用貸借の借主として得られる利益も早めに失った点が、損害賠償の請求額に反映されることがわかります。つまり、使用貸借がどれほど存続するかのおおまかな期間を事前に予測できないような事案(契約)では、賠償額の算定は非常に困難になるということです。
不動産の使用貸借は、節税対策になるか?
例えば、土地を無償で子供に貸して、その土地に子供がマイホームを建てるというケースは多く見られます。土地を貸す際に親子間で金銭のやり取りが行われていませんから、典型的な使用貸借といえるでしょう。このケースで気になるのは贈与税の問題です。子供は土地を無料で使える分だけ得をしているわけですから「資産を贈与されている」と言い換えることもできます。しかし、実際に贈与税が課せられることはありません。相続税基本通達の第9条で「利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとする」とただし書きされているように、それほどきびしく言及されてはいないことが原因と考えられます。
このことから「使用貸借は節税対策として有効」に思えますが、土地を賃貸借した場合と異なり、「土地の評価額を減少させる効果がない」ために、相続税を節税できないデメリットがあります。
例えば、土地を賃貸借した場合は、路線価に基づく不動産評価額に対して借地権割合が適用され、更地であるときよりも評価額が減少します。借地権割合には7段階ありますから、最大で70%の減少となります。しかし、使用貸借は借地権には該当しませんので、借地権割合も適用できず更地評価となるのです。ちなみに、使用貸借の土地に借主が家を建て、それを借家として第三者に貸したとしても更地評価となるので注意してください。
土地評価額を減少させるためには、使用貸借ではなく賃貸借契約にして、第三者に貸すのが確実です。土地をそのまま贈与するよりも、賃貸マンションを建ててから渡すほうが、結果的に税金の負担が軽くなることもあります。
民法大改正(2020年施行見込み)と使用貸借
2020年に施行予定の改正民法の中で、使用貸借に関する最も大きな改正点は、「要物契約」から「諾成契約」に変更となった点です。
従来の民法593条では「使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる」と規定していました。これは、貸主と借主のあいだで使用貸借の合意や契約書の取り交わしがあっただけでは契約は成立せず、目的物の引渡しがあって初めて成立することを意味しています。つまり、これまでの民法では、目的物が引き渡されるまで「契約上の義務」が発生しないため、安全な取引きとは言い切れない状況がありました。
この問題をクリアするため、改正民法593条では「使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる」としました。これにより、貸主が一方的に引き受けていた「不動産を引渡すまでのあいだに生じる諸問題」が、借主にも発生することになります。
ただし、軽率な使用貸借契約の成立を予防し、貸主を保護する趣旨から「目的物の引渡し前であれば、貸主は契約解除できる」という条文が加わりました。なお、書面によって締結された使用貸借契約については、引渡し前でも貸主は契約解除できません。契約書まで作成していれば、もはや軽率とはいえないからです。
また、借主が使用貸借の本旨に従わない使い方をしたことによって損害が発生した場合、貸主は損害賠償を請求できますが、従来の民法では目的物の返還を受けてから1年後までに請求しなければならないという期間制限が設けられていました。改正民法600条2項ではこの期間制限が外れ、返還から1年以上経過しても損害賠償請求できるようになるなど、貸主保護の方針が敷かれています。