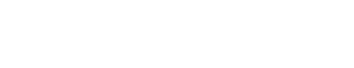BER(損益分岐点/Break Even Ratio)
「BER(Break Even Ratio)」は、いわば「均衡が破られる比率」というほどの意味であり、日本語では「損益分岐点」と訳されています。ビジネスにおいては、利益と損失が等しくなり、営業利益が上がるかどうかのボーダーラインとなる売上金額を指します。
BERの一般論
ビジネスとは、売上さえあればいいものではありません。「営業利益を獲得し続けられる」だけの売上を上げていなければならないのです。ビジネスを長期的に続けていく上で、最低限必要な売上目標を数値化させることが、BERを算出する上での実質的な意義といえます。
よって、BERが高いビジネスほど、持続性を保つためのハードルが高く、経営リスクが大きくなることを意味します。BERが低いビジネスは、経営リスクを小さく収められますが、その分、参入障壁も低く、ライバル業者が増えやすい業態ともいえるでしょう。潜在的な需要が高い業態であれば、多少ライバルが増えても社会的な受け皿がありますが、需要が高いといえない業態では、BERの低さこそがリスクになる危険もあります。
営業利益と限界利益
営業利益とは、「(商品の価格-固定費-変動費)×販売数量」の式で算出できます。
「固定費(固定コスト)」は、売上が動いても変化しないコストを意味します。店舗の家賃や従業員の給与など、たとえ売上がゼロでも支払わなければならない費用です。固定コストに満たない売上に甘んじている限り営業利益は出せませんが、売上が固定コストを上回る一定のラインを超えれば、営業利益は一気に伸びていきます。
「変動費(変動コスト)」は、売上の増加に合わせて増えるコストを意味します。代表的な変動費としては、製造業では材料費や外注費など、小売業では商品の仕入れ額などが該当します。一般的に、損益分岐点にあたる売上高は、「固定費÷(1-変動費÷売上高)」の式で算出できます。
また、前述した損益分岐点売上高の計算式の分母にあたる「1-変動費÷売上高」のことを、限界利益率といいます。例えば、70円の商品を仕入れて100円で販売した場合、限界利益は30円であり、限界利益率は30%となります。粗利益も営業利益も、限界利益を上回ることはありません。その事業で利益を得ることができる「論理的な上限の壁が限界利益」なのです。
売上が減っても経営を継続できる余裕を示す数値
黒字となっている事業で、たとえ今より売上が減ったとしても、損益分岐点を割り込まない「余裕値(バッファ)」を示す割合のことを、経営安全率といいます。経営安全率は「1-損益分岐点売上高÷現在の売上高」で算出することができます。経営安全率が30%であれば、将来的に今よりも売上が30%下がっても赤字にならないのです。売上が若干下がっても慌てず、落ち着いて集客準備に向けての対策を練ることができるでしょう。また、経営安全率はさらにシンプルに、「営業利益率÷限界利益率」の式でも算出できます。営業利益率は、売上高に占める営業利益の割合を指します。
不動産投資のBER
不動産投資の場合、BERは「投資物件をどれだけ安全に運用しうるか」を示す指標として利用されています。
不動産投資での固定費は、「物件の建設費」や「メンテナンス費用」「税金関係」となります。また、アパートやマンションの経営では、全体の固定費だけでなく「一戸あたりの固定費」も把握しておく必要があります。ビルやホテル、大型マンションを建設するような不動産投資では、「家賃の引き上げ」「部屋数を増やす」、または「集客して稼働率を上げる」ことで、多額の家賃収入を確保できます。ただ、初期投資としての物件建設費用が高くなるため、固定費が引き上がりBERも高まるため、必然的に経営リスクも高まっていくといえます。
家賃収入による売上金額がBERに満たなければ赤字に直結しますので、得られる家賃収入(利益)の見込額を、維持費やローン返済などの「運用コスト(損失)」と照らし合わせて、事前にしっかりと吟味しておかなければなりません。投資不動産を将来的に処分することを前提とするなら、投資金額を回収できる売却金額も考え合わせた上で、BERを計算することになります。
不動産投資のBERで重要なのは利回り
不動産投資は比較的長期にわたる投資であり、将来の景気や地価、ニーズなどによって収益性が変動します。そのため、将来的な利益や損失を正確に計算するのは困難といえます。不確定要素が多く絡んでくる不動産投資では、「たとえ家賃収入が落ち込んでも、いくらまでなら損をしないか」というボーダーラインとしてBERを把握しておくことが、成功と失敗の分岐点となりうるのです。
なお、金融機関からの融資を受けた上で不動産投資をする場合、その損益分岐点の計算式は以下のとおりとなります。
BER=(ADS+OPEX)÷GPI
【ADS(年間負債返済額)】ローンに対する年間の返済総額
【OPEX(運営費)
】不動産物件を維持・管理・運営するために必要な年間の総費用
【GPI(総潜在賃料収入)
】投資不動産が満室のときに得られる年間の総潜在賃料収入額
不動産投資でのBERを算出するときに重要となるのが「利回り」です。利回りは、「投資額に対し、家賃収入で回収できる利益」がどれほど確保できるかを表す指標です。つまり、利回りが大きい物件であるほど、「投資金額に対して家賃収入が上回るまでの期間が短くなる」ため、損をするリスクは小さくなります。
BERを制する者が、ビジネスや不動産経営を制する
不動産投資に限らず、経営の目的は「1円でもいいので利益を残すこと」です。さまざまな費用を足し合わせ、あらゆる費用を差し引いて残った額がプラスであれば、余裕をもって事業を継続できます。一方、マイナスは赤字ですから、内部留保や外部からの借入れなどで埋め合わせなければなりません。
つまり、「収支トントン」の状態を示すBERは、ビジネスを安心して継続できるかどうかの分かれ目になりうるのです。もちろん、正確で精密な計算は、プロの会計士や経理担当者に任せて構いませんが、不動産投資家(ビジネスオーナー)も、大まかな範囲でBERの動向を把握しておくことが、ビジネス継続の鍵といえるでしょう。中でも「固定費と変動費の区別」は、できるようにしておきたいものです。
また、収入に関しては「操業度」という考え方を覚えておくといいでしょう。工場で例えると、設備や機械の生産能力が100%の限界と比べてどの程度発揮されているのかを示すものです。生産機械が10台ある場合、7台の機械が動いている状態を「操業度70%(70%稼働)」といい、成果物の数も70%となるため、事業収入も70%となります。
もし、操業度70%で損益分岐点を超え黒字になるのであれば、商品の値下げを断行しても、当分持ちこたえられるでしょう。このように、BERを把握しておけば、どこまで価格を下げられるのかの限界点も合理的に知ることができるのです。
操業度を応用して、賃貸物件の事業収入をとらえることもできます。物件の部屋数に対する入居率を稼働率に置き換えるのです(満室であれば稼働率は100%)。
物件の入居率が70%でBERを上回る場合、理論的には1年のうち7割の日数が過ぎた時点で、それ以降の家賃収入がすべて利益になる計算です。この状態であれば、家賃の値下げやフリーレントを行うことで残りの部屋を埋めることも可能ですし、既存の入居者から家賃交渉を迫られたときも、心理的に余裕を持って交渉に臨めるでしょう。
「損益分岐図グラフ」だけで経営判断を行うことは危険
損益分岐点(BER)の把握をするために有効な線グラフのことを、損益分岐図といいます。縦軸に売上高やコストの金額、横軸に生産・販売数量を取り、売上高の比例直線と総コストの比例直線が交わったところを横軸に垂直に下ろすと、そこが損益分岐となる販売数量となるのです。
これは、財務分析の基本となるグラフで、売上数量をゼロからたどって右に進んでいくのですが、総コストの線が売上高の線を上回っているあいだは、損失が発生している状態です。さらに右に進むと、売上線と総コスト線が交わって入れ替わりますが、ここから利益が発生するのです。この、2つの線が交わったところが損益分岐点となります。
グラフにするとわかりやすいですが、売上線の傾きを上げる(単価を上げるなど)と損益分岐点が下がり、利益を出しやすくなります。一方で、総コスト線の傾きを下げても(生産効率を上げるなど)損益分岐点が下がり、やはり利益を出しやすくなります。
グラフ上では、簡単に売上数量を増やし、生産効率を上げられますが、これは経営判断の上で陥りやすい落とし穴です。実際に売上を増やすには、事業の常連客・固定客を増やしたり、客単価を上げたりする必要がありますし、生産効率を上げるには、従業員教育や設備投資などの追加コストが求められます。
もちろん、不動産経営も同様で、入居者を増やす、家賃を上げることは簡単ではありません。入居者を増やすために不動産業者への広告費を増やしたり、より良い設備を導入したりするためには、コストがかかるからです。
紙の上だけで経営判断を行うと、それを実現するための努力と投資の裏付けを忘れがちになりますので、気を付けたいところです。