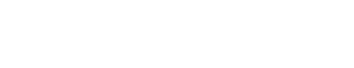賃借権
(ちんしゃくけん)
「賃借権」とは、他人の所有物について金銭を負担することを対価にして、使用したり収益を得たりすることができる権利を意味します。社会的には不動産の賃借権が重要な位置付けとされていますが、動産の賃借権もビジネスとして広く行われています(自動車の賃貸借事業である「レンタカー」や、DVDの賃貸借事業である「レンタルDVD」など)。権利の類型としては、地上権がこれに似ていますが、建物や樹木を所有するための土地の使用権というように、「目的が限定されている」点や「無償の契約も可能」な点などが、賃借権と異なります。
賃借人の権利
賃借権を持つ者(借主・賃借人)は、その目的物を使用し、収益を得る権利があります(ただし、転貸が制限される場合があるときは異なります)。また、土地に関する賃借権(借地権)を持つ者が、借りているあいだに建物を建てたとき、賃貸借契約の終了時に、その建物を買い取るよう賃貸人(貸主)に請求することができます。これを「建物買取請求権」といいます。ただし、この場合に賃貸人が支払う額に借地権価格を含める必要はないため、建物の建築に要した額を大幅に下回ることになります。
さらに、建物に関する賃借権(借家権)を持つ者が、借りているあいだに畳や戸、水道などのインフラ設備、エアコンなどを備え付けた場合には、賃貸借契約の終了時に、これらの設備を買い取るよう賃貸人に請求することができます。これを「造作買取請求権」といいます。
賃借人の義務
賃貸借契約を結んだ以上、賃借人は「契約で定められた賃料を賃貸人に支払う義務」を負います。また、賃貸借契約が終了したとき、賃借人は「その目的物を賃貸人に返還する(不動産の場合は明け渡す)義務」を負います。ただし、建物買取請求権や造作買取請求権がある場合で、賃貸人がその対価を支払わないあいだは、賃借人はその目的物を明け渡す必要はないとされています。
不動産の賃借権は法律で保護される
不動産の賃借権のうち、土地の賃借権を「借地権」、建物の賃借権を「借家権」と呼びます。そして、借家権と建物を所有する目的の借地権は、借地借家法による特別な保護が定められています。
不動産の貸主と借主では、古今東西貸主の立場が強いのが世の常です。人が満足に暮らすためには、まず住む場所を確保しなければなりませんし、食い扶持を得るための田畑や牧場などの農作業場を確保する必要がある場合もそうです。そのために、賃貸借契約では、借り手が一方的に不利な契約を結ばされることが多かったのです。そこで、借地借家法では、借地権(建物所有目的)と借家権を持つ人に肩入れすることで、全体のバランスを図っています。
民法の一般原則によれば、借地権や借家権は、以下のような特徴があります。
【対抗力がない】
貸し手が土地や建物を他の人に売り渡した場合、借り手は出て行かなければならない。
【自由に転貸できない】
賃貸借契約では、賃借人が「目的物を大切に使ってくれる」「賃料をしっかり払ってくれる」「(不動産の賃貸借の場合)近隣に迷惑をかけない」など、貸主と借主の信頼関係が重要だとされている。よって、借主の立場が入れ替わるときは、貸主の承諾を得なければならず、無断で借主が交替することは、賃貸借契約を解除する理由となる(民法612条)。
【存続期間が短い】
賃貸借の期限は20年が上限とされている(民法604条)。また、期間を定めていない土地の賃貸借は1年間、建物の賃貸借は、解約の申入れから3ヵ月間は存続することになっている(民法617条1項1及び2号)。
しかし、これらの原則が借地借家法で次のように修正されています。
【対抗力が生じる】
建物所有目的の借地権を持っている人は、その建物について登記をしていれば、土地の所有者が変わったとしても、引き続き借地権を新たな所有者に対して主張して、利用し(住み)続けることができます。また、借家権を持っている人は、たとえ建物の所有者が変わったとしても、その建物に居住している事実があるだけで、借家権を新たな所有者に対して主張して、住み続けることができます。
【転貸の一部自由化】
建物所有目的の借地権に限っては、たとえ貸主の承諾を得られなくても、借主は裁判所に申し立てて、貸主の承諾に代わる転貸の許可を取ることができます(借地借家法19条1項)。
【存続期間の延長】
借地権は存続期限の上限が30年とされ、さらに貸主と借主の合意があれば延長することができます(借地借家法3条)。期間を定めなかった場合は、一律に存続期間30年の借地権とされます。また、30年以上の期間を定めることも可能です。
借家権は、民法の原則よりも解約申し入れ期間が延長されています。解約申入れから6ヵ月間は猶予されることで、次の住まいを探す時間に余裕を持てるのです。なお、不動産投資という観点から見れば、賃借権は以下のようなメリットやデメリットもあります。
- <メリット>
- ・所有権に比べて価格が安くなるので、不動産購入額を低く抑えられる
- ・所有権は地主にあるので、借地権を取得しても土地の取得税は発生しない
- ・登記費用も発生しないので、不動産購入時の諸費用を低く抑えられる
- ・固定資産税・ 都市計画税の納税義務者は地主であるため、土地の固定資産税・都市計画税の負担がない
- <デメリット>
- ・地代の負担がある(一般的に固定資産税の3~4倍程度)
- ・更新時には更新料が必要になる(借地権価格の5~10%または更地価格の2~6%程度)
- ・建て替えや譲渡の場合は地主の承諾が必要となる
- ・担保評価が低いため、借地権への融資を取り扱わない金融機関が多く、借り入れしにくい
- ・第三者に売却しづらい
賃借人の地位を高めた結果生じた「賃借権の物権化現象」
賃借権は、本来は特定の人から特定の人に請求する「債権」としての性質を持っています。つまり、賃借人が賃貸人に対して、物件に住まわせてもらうこと、あるいは使用させてもらうことを求めるのみで、それ以外の人に権利を主張できないのが原則です。
しかし、特に不動産に関する賃借権がそのように弱い権利の場合、権利を他人に主張できなくなった賃借人が路頭に迷ってしまい、生存に関する基本的人権が脅かされるおそれが生じます。
そこで、賃借人の地位を高め、保護するために、「借地借家法」での特別規定が設けられています。例えば、土地に関する借地権の登記をしていなくても、建物の借家権を登記していれば土地の所有者に権利を主張できたり(借地借家法10条1項)、建物の借家権の登記をしていなくても、その建物を事実上占有していれば第三者に対して権利を主張できたりする(同31条)、といった特別な保護を施し、賃借人が引き続き日常生活を維持できるように配慮しているのです。
ほかにも、農地の賃借権では、賃貸人(農地の所有者など)が解約する場合には、都道府県知事の許可を得なければならないとして、賃借人を特別に保護する規定が農地法に設けられています(農地法18条)。
本来の賃借権は「債権」ですから、賃貸人と賃借人のあいだでしか効力を発揮しません。しかし、賃借権の法的保護が進み、第三者に対して権利を主張できる「物権」に近いものとなりました。このことを「賃借権の物権化現象」といいます。
非正常な賃借権の問題を解決するための「明渡猶予制度」
かつて民法395条は、山林10年・土地5年・建物3年・動産6ヵ月を超えない期間の賃借権を「短期賃借権」としていました。先に抵当権の登記を行った債権者がいる場合でも、賃借権に関する登記がなくても、濫用的な目的でない限り、いわば割り込み的に物件を占有していれば、抵当権者に対抗できると定められていたのです。
しかし、この短期賃借権に関する特別規定を悪用し、正当な抵当権者を妨害するケースが現れるようになります。濫用的な短期賃借権は「非正常な賃借権」として、抵当権に対抗できないことになっていましたが、濫用的かどうかの立証でトラブルになることもありました。
この短期賃借権に関する特別規定は、2004年3月をもって廃止され、「明渡猶予制度」と差し替えられました。ある物件について抵当権に劣る賃借権を持っている賃借人は、抵当権が実行されて物件が競売にかかって買受人が現れたとしても、賃借人が競売開始前から物件の使用収益をしていれば(あるいは強制管理または担保不動産収益執行の管理人が、競売手続きの開始後にした賃貸借により使用収益をしていれば)、あと6ヵ月間は住み続けることができるようにしたのです。
ただし、この明渡猶予制度が適用される賃借権であっても、さらには抵当権設定に先だって対抗要件を備えた優先的な賃借権であっても、抵当権の執行妨害目的が認められるなど、実態が濫用的であれば「非正常な賃借権」として、6ヵ月間の猶予が認められない可能性があります。
実際には、執行官が以下のような事情を現状調査することによって、「非正常な賃借権」かどうかを判断することになります(民事執行法57条1項、民事執行規則29条1項)。
- ・占有主体の問題:賃借権に基づいて、誰が占有しているのか
- ・占有権原の問題:その占有が所有者でない第三者による占有の場合、どのような権原で占有しているか
- ・対抗の可否:その占有権原が買受人に対抗できるものなのか
民法大改正(2020年施行見込み)と賃借権
賃借権に関するルールは、民法で規定されています。そのうち、2020年の民法大改正で契約に関する規定が大幅に変更されることを受けて、賃借権をめぐるルールも基本から大きく変わります。
<賃借権の存続期間>
現在の法律において、賃貸借契約の存続期間は原則として最高20年であり(民法604条)、20年を超える存続期間を定めても無効になります(ただし、借地借家法の適用を受ける土地や建物の賃貸借については、例外的に存続期間の上限はありません)。
物権である「地上権」(民法265条~269条の二)の存続期間の上限は50年ですが、借地借家法と旧借地法で保護されて強力になった「賃借権」の存続期間を短くすることで、双方のバランスをとったものとされています。
地上権とは、建造物を建てるために他人の土地を利用させてもらう物権です。用途としては賃借権と重なる部分もありますが、無償でも設定可能など、賃借権にはない特徴もあります。
ただし、借地借家法の影響で「賃借権の物権化現象」が固定化されるなど、民法ができた明治時代にはなかった傾向も見られるようになりました。賃借権と地上権を厳格に区別する必要性が減っている現状を重く見て、借地借家法の適用を受けない土地の賃貸借(例えば、ソーラーパネルや駐車場などの工作物を設置する土地賃貸借)について、上限を50年とする法改正がなされています。
<賃借人の物件修繕権>
従来の民法では、賃貸借で借りている物件に雨漏りなどの不具合が生じた場合、606条で「賃貸人の修繕義務」を規定しているにとどまっています。つまり、賃借人の判断で勝手に直すことはできず、賃貸人に修繕をお願いしなければならないのです。もし、賃借人が無断修繕すれば、他人の所有物の原状を勝手に変更する信頼関係の破壊があったとして、賃貸人から契約解除が通告されてもおかしくありません。
仮に緊急を要する不具合であっても、賃貸人の対応を待つ必要があります。賃借人は現状に我慢するか、友人の家に泊めてもらったりホテル住まいをしたりするなどの対応をとらざるをえないのです。
これは、「賃借人にとって酷なルール」であると指摘され続けてきました。そこで改正民法では、607条の2で「賃借人の修繕権」を定めました。賃借人が賃貸人に修繕を要求(通知)したあと、賃貸人が相当の期間内に修繕の対応をしない、あるいは賃借人や物件自体に緊急の修繕を要する差し迫った事情がある場合は、賃借人自身で合法的に修繕できるようになったのです。
ただし、賃借人の修繕権の内容は、具体的に定められていません。例えば、賃借人が無断で通常よりも高価な修繕を行ったり、物件の内観・外観が変わるような修繕を施したりした場合にも、その修繕を賃貸人に認めさせることができるかといった問題が考えられます。修繕権については、今後、判例が積み重なっていくことが予想されますが、賃貸人と賃借人のトラブルを避けるため、修繕の範囲を具体的にして契約書に盛り込む、一部制約を設けるといった対応が求められるでしょう。
<一部滅失による賃料減額>
民法611条は、賃貸借の目的物が一部「滅失」した場合には、借主が貸主に対して賃料減額請求権を行使し、地代や家賃を実情に見合う額に減らすよう求めることができると定めています。滅失の判断は難しいところですが、賃貸借の土地の一部が国によって収用を受けた場合や、賃貸借の建物が雨漏りして床の一部が使えない場合は適用されると考えられてきました。
このように、従来は解釈論を持ち出して解決してきた問題を、改正民法611条では、一部滅失のほかに「一部使用収益不能」の場合も含めることで明文化しました。また、賃料減額は貸主への請求を行わなければ効果が発生しませんでしたが、改正民法では、一部滅失や一部収益不能の事実を立証できれば減額できる(請求不要)ものとして借主を保護しています。