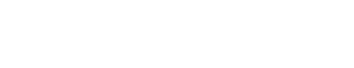譲渡税
「譲渡税(譲渡所得税)」とは、不動産や株式などの資産を売却したことによって生じた譲渡所得(利益)に対してかかる税金のことです。昨今では、ビットコインなどの仮想通貨を、仮想通貨交換業(改正資金決済法2条7項)で日本円に交換したときに得た利益も、譲渡税の課税対象となりうるとされています。
譲渡税の計算
譲渡所得に対しては、ほかの所得と分離して「 所得税 」と「住民税」が課税されます(2037年までは復興特別所得税も課税されます)。なお、譲渡所得がマイナスの場合には、課税されることはありません。
譲渡益に対する税率はほかの所得と分離して、分離課税の税率となり、対象となる不動産の用途や所有期間により税率が異なります。譲渡所得税額は、以下の計算式にて算出することができます。
譲渡所得税=課税譲渡所得×譲渡所得税の税率
また、課税譲渡所得は以下の計算式にて算出することができます。
課税譲渡所得=売却価格-(購入価格+購入時にかかった取得費+売却時にかかった売却費)-譲渡所得特別控除
「売却価格」については、安価すぎる場合には注意が必要です。土地や建物の売却先が企業などの法人であり、しかも時価の2分の1を下回った価格で売却したときには、その土地や建物の「時価」を売却価格として設定しなければなりません。時価の半分未満で譲り渡してしまった場合は、譲渡所得税がかえって高く課せられてしまう可能性があるのです。
ここでいう「取得費」には、購入に伴う手数料だけでなく、購入後に支出した改良費や設備費も含みます。建物の取得費の場合は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引きます。また、取得費が売却価格の5%に満たない場合、あるいは取得費が不明な場合は、売却価格の5%を「概算取得費」として計上することができます。
そして、「売却費」には、不動産を売り渡した際の仲介手数料や測量費、売買契約書の収入印紙代が含まれます。もし、売却するときに借家人などに支払った立退料があれば、それも売却費に含みますし、建物を取り壊して土地を売却した場合には、建物の解体費も売却費として計上することができます。
次に、「譲渡所得特別控除」ですが、以下のようなものがあります。
(1)公共事業などのために土地建物を売った場合の5,000万円の特別控除の特例
(2)マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円の特別控除の特例
(3)特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合の2,000万円の特別控除の特例
(4)特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合の1,500万円の特別控除の特例
(5)2009~2010年に取得した国内にある土地を譲渡した場合の1,000万円の特別控除の特例
(6)農地保有の合理化などのために土地を売った場合の800万円の特別控除の特例
それぞれの特別控除額は、特例が適用される事情ごとの「譲渡益」の額が上限となり、総計としては、その年の譲渡益の全体を通じて、5,000万円が上限となります。
控除は(1)から(6)の順に行い、5,000万円に達したらストップとなります。
(2)のマイホーム控除は、不動産投資のオーナーで、物件に居住している場合でも適用されない可能性がありますので、念のため税理士などの専門家にご相談ください。
(5)の特別控除は、不動産の流通を促進させ、地価の下落が続く「資産デフレ」を食い止めるために導入された政策的なものとなります。
譲渡所得税の税率は所有期間によって変わる
譲渡所得税を求める計算式「譲渡所得税=課税譲渡所得×譲渡所得税の税率」における税率は、以下のように決められます。
長期譲渡所得:15%(+住民税5%)
短期譲渡所得:30%(+住民税9%)
※ほかにも源泉徴収税額の2.1%の復興特別所得税が、2037年まで課税される予定です。
その不動産を譲渡した年の1月1日時点で、その不動産の所有期間が5年を超えていれば、譲渡によって得られた売却益は「長期譲渡所得」となり、5年以下であれば「短期譲渡所得」となるのです。
例えば、2011年5月に取得した土地を2016年10月に売却した場合、実際の所有期間は5年を超過していますが、2016年1月1日時点では5年以下となっていますので、5年以下での譲渡となってしまいます。
なお、長期譲渡所得となる場合でも、所有期間が10年を超えていて、課税譲渡所得6,000万円以下であれば、所得税10%+復興特別所得税(+住民税4%)という特例が適用されます。もし、6,000万円を超える売却益を得ていても、6,000万円までの部分は、この特例を適用して税の減軽を受けることができます。
一方で、不動産を所有期間5年以下で売却した場合、39%(所得税30%+住民税9%)という高い税率が課せられます。これは、投機的な土地売買を抑制するための措置となります。
なお、不動産を売却することによって損失を招くことも考えられます。不動産の売却で損失が出た場合、一定の要件を満たせば、以下の2つの特例を利用できます。
(1)居住用不動産(マイホーム)に買換えをした等の場合、譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
(2)特定居住用財産(住宅ローンが残っているマイホーム)の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
(1)は、5年を超える長期的保有のマイホームを譲渡したときに生じた譲渡損失の金額について、一定の要件を満たす場合に限り、譲渡をした年に得られた、不動産所得ではないほかの所得(事業所得や給与所得など)との損益通算をすることができ、さらに、これらの通算を行ってもなお控除しきれない損失の金額については、その譲渡の年の翌年以後3年間にわたり繰り越して控除することができるという特例です。
(2)は、(1)よりもきびしくない要件で、同様の特例を認めるものです。「譲渡対価-取得費等」の額と、「住宅ローンの残債-譲渡対価」の額で比べて、いずれか少ないほうを「売却損」として計上することになります。
この特例を利用することによって、以下のようなメリットがあります。
・不動産を売却した年度の給与など、ほかの所得と損益通算することで支払う税金が安くなる。
・売却年度に損失の控除がしきれなかった場合、譲渡の年の翌年以後、最大3年間繰り越すことができる。そのため、翌年以降に支払う税金が安くなる可能性がある。
いずれにしても、不動産売却の際には可能な限り損失を出さないように、さまざまな特例を利用するといいでしょう。
実はしっかりリンクしている譲渡税と相続税
日本の所得税法では、相続によって取得した不動産であっても、所得に該当すると考えられています。相続によって取得者(相続人)の経済的利益が増すからです。ただし、その場合に取得した不動産は相続税の課税対象でもありますので、二重課税にならないかが問題となります。
所得税法では、「相続、遺贈又は個人からの贈与によって取得するもの」を非課税所得(9条1項16号)とし、相続財産は「所得ではあるけれども課税しない」という方針を明らかにしています。
一方で、相続税法は、相続・遺贈または贈与によって取得した財産を相続税(または贈与税)の課税対象としている(1条の3、1条の4)ため、解釈によっては両者の課税対象が重複することで二重課税が生じ、相続人に不当に重い税負担が課されることになるのです。
この二重課税の問題では、不動産を相続で取得した相続人が、その不動産を他人に売却して値上がり益を得ていたときの課税について裁判例が出ています。
この際、相続不動産を売却して得た金銭のうち、値上がり益に該当する部分について所得税が課されることについては争われませんでした。ただ、値上がり益を除く不動産の相続税評価額については、所得税法の「非課税所得」にあたるとして、相続人が国を相手取る形で争われたのです。
ほぼ同時期に、類似の2件の訴えがありました。東京高等裁判所2013年11月21日判決(原審は東京地方裁判所2013年6月20日判決)、並びに東京地方裁判所2013年7月26日判決では、結論として「非課税所得ではない」として、相続人側が敗訴しました。
裁判所の考え方としては、まず、相続の開始(被相続人の死亡)によって、相続不動産は「抽象的に」譲渡所得税の課税対象になりますが、相続人において具体的にどれほどの額の資産が増加したのかは、具体的に明らかになっていないため、ひとまず留保しているという立場を取ります。さらにその後、確定申告なり不動産の譲渡なりで、具体的な資産増加額が明らかになるわけですが、その時点までの相続人が不動産を保有していた期間中に発生し、蓄積した資産の増加益も含めて課税されることが、所得税法の制度趣旨として予定されている(初めから組み込まれている)との考えを示しています。
さらに、それが二重課税であるとの批判に対しては、不動産の譲渡益は、本来、被相続人が保有するものであって、その死亡をきっかけにたまたま相続人が受け取っているに過ぎず、その譲渡益に所得税が課されるとしても、相続税との二重課税の関係にはないと結論付けました。
つまり、相続した不動産を間もなく売却すると、その売却で受け取った全額について、相続税に加えて所得税が課されることになりますので、くれぐれもご注意ください。
たとえ法理論的に二重課税ではなくても、同一の不動産について2種の課税がなされる実態があるのは間違いありません。課税当局は、諸外国の課税ルールを参考にしながら、国民の間の不公平感を解消する制度設計を行っていく努力を怠るべきではないでしょう。