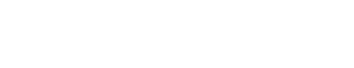敷金返還
「敷金」とは、不動産の賃貸借契約で、賃貸人に対する家賃など、契約によって発生するあらゆる債務を担保するため、賃借人から賃貸人に交付される金銭のことです。契約終了時に利息をつけることなく、賃貸人から賃借人へ返還されるべきものでもあります。
この定義からわかるように、不動産の貸主にとって敷金は、契約終了時に返還することを前提にしていなければいけません。
ただし、あくまでも「担保」として貸主が預かっているものですから、必ずしも全額返還する義務があるわけではありません。契約終了時に借主が滞納している家賃や、通常の経年劣化として許容できない破壊や改造が物件に加わっている場合、貸主は敷金からその損害額をあてることができ、残りを借主へ返還することになります。また、損害額が敷金を上回っている場合、不足分を損害賠償や不当利得として、借主に請求することができます。
なお、敷金という名称でなく、別の名目(保証料など)であっても、敷金の定義にあてはまる金銭であれば、法律上は敷金として扱われることも覚えておきましょう。
また、契約終了後に貸主が敷金を不当に返さない場合、借主は敷金返還まで物件を明け渡さないという抵抗を主張することができます。これを「同時履行の抗弁権」(民法533条)といいます。
「敷引き」について
賃貸借契約を結ぶとき、その契約終了時に、敷金の一部のみを返還し、残りを賃貸人が受領したままにする特約をいっしょに結ぶことがあります(契約書の中に盛り込まれていることもあります)。
例えば、貸主が契約時に敷金として30万円預かった場合、契約終了時に30万円を返還するのが原則ですが、最初から「敷引き10万円」と定めておき、最大20万円の返還で足りる特別契約を結ぶというものです。これを「敷引き特約」と呼びます。
敷金については、貸主と借主がお互いに納得していれば、どのような契約を結んでも原則として有効ですから、敷引き契約も有効ということになります。この敷引き特約は、東京などの首都圏ではあまり見られませんが、大阪府や兵庫県では一般的なものとして定着しています。
敷引きについては、「賃貸借契約成立の謝礼として、借主が負担するもの」とする考え方が基本にあるようです。しかし、深刻な住宅不足の時代ならまだしも、人口減少の時代を迎え、選り好みをしなければ物件はたくさんありますので、敷引きを特別な謝礼と考えるのは無理があります。
また、「物件の自然な損耗を修繕する費用」とする説もあります。とはいえ、通常の修繕費は家賃の範囲内で貸主が負担すべきものであり(民法606条1項)、敷引きによって借主が負担することは賃貸借契約全体のバランスを欠いた状態といえるでしょう。
借主に負担を強いる敷引き契約は「法的に無効」であると主張し、裁判に臨んでいる人もいます。「消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項で」「消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする」(消費者契約法10条)に該当するか否かが問われました。
この裁判は最高裁まで争われ、敷引き特約が賃借人の義務を加重し、賃借人の利益を一方的に害するものであるため、消費者契約法10条により無効であると結論付けています(最高裁判所2011年3月24日判決)。今後、所有物件の借主に敷引き特約の締結を求めることは避けるべきといえるでしょう。
民法大改正(2020年施行見込み)と敷金
敷金は、これまで民法においては、第316条と619条2項において登場する言葉でしたが、公式に定義されていたわけではありませんでした。その具体的内容は、貸主と借主のあいだで締結する賃貸借契約の中で、個別に定められている位置付けだったのです。両者の力関係の差から、多くは借主にとって不当な、あるいは曖昧不明瞭な敷金契約が結ばれていることも少なくありませんでした。しかし、2017年5月に国会で可決、成立した改正民法の中で、敷金は具体化されました。
民法の第2章 第7節 第4款として、敷金という専用カテゴリーが新設されたのです。ここには、世の中に敷金をめぐるトラブルが多数発生していることに対する起草者の一種の危機感が表れているといえるでしょう。そして、戦前から蓄積されてきた多数の判例による考え方が、民法の条文として正式に規定されたのです。
新民法622条の2 第1項で、敷金は「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、借主が貸主に交付する金銭」と定義されました。これは、大正時代の判例をなぞっているもので、現代にも脈々と引き継がれています。
そして、次に該当する場合には、敷金の額から、賃貸借に基づいて生じた借主の貸主に対する金銭の給付を目的とする債務(借主が滞納している家賃や、借主の用法違反によって生じた相当規模の破損の修繕費)を差し引いた残額を、貸主は借主に返還しなければならないと定めています。
- ・賃貸借が終了し、且つ、賃貸物の返還を受けたとき(賃貸物が建物であれば、借主が明け渡したとき)
- ・借主が適法に賃借権を他者へ譲り渡したとき
特に関西地方を中心に、借主の債務の有無にかかわらず、契約終了時には敷金を全額返さず、礼金代わりに貸主が一部を預かるという「敷引き特約」が結ばれている場合があります。新民法の規定では、よほどの事情がない限り、敷引き特約は無効と認定される危険性があります。
また、貸主が負っている、敷金返還債務は「賃貸借の目的物となっている不動産を、貸主が第三者に譲渡し、貸主たる地位も移転したとき、賃貸返還債務も新貸主(不動産を譲り受けた第三者)が引き受ける」と規定されています(新民法605条の2 第4項)。
貸主たる地位は、原則として借主の同意を得ずとも、賃貸借の目的不動産について借主が対抗要件を備えていない場合、その不動産が取引きされた時点で、いわば自動的に新しい所有者に移ります(新民法605条の2、605条の3)。借主が賃借権の対抗要件を備えている場合は、以下のとおりです。
- <借主による賃借権の対抗要件>
- ・借主が目的不動産について賃借権の登記をしている場合
- ・土地の賃借権の登記をしていなくても、建物の所有権登記をしている場合(借地借家法10条1項)
- ・建物の賃借権の登記をしていなくても、その建物を事実上占有している場合(借地借家法31条)
さらに、この敷金返還債務が発生する前段階で、借主が貸主に対する債務を履行しないときは、貸主は敷金をその債務の弁済に充当することができると定めました。また、借主がその充当を貸主に請求することができないとも位置付けられています(新民法622条の2 第2項)。
つまり、借主が家賃の支払いを滞らせた場合、貸主の判断で「預かっている敷金から滞納分を差し引くから、退去時に受け取れる額は減ります」と借主に告知することはできますが、借主から「今、持ち合わせがなくて家賃を払えないから、敷金から差し引いておいてください」と請求することはできないのです。